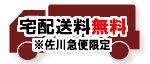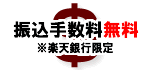- 買取の特集(トップ)
- 時代小説、歴史小説高額買取品
木挽町のあだ討ちの参考買取価格
◎参考買取価格は新品同様の状態を前提としています。
◎買取時は、状態や需要、在庫数等を再考慮して査定します。
◎参考買取価格は常に変動しているため、目安とお考え下さい。
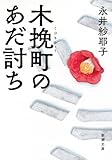
木挽町のあだ討ちは、永井紗耶子による時代小説で、江戸期・芝居町「木挽町」を舞台に仇討ち事件の真相を浮かび上がらせる物語です。物語は語り手が入れ替わる群像形式で進行し、ひとつの事件を軸にそれぞれの人生が交錯する構造を持っています。
雪の降る夜、木挽町の舞台裏で若衆・菊之助が父を殺めた下男を切り、血まみれの首を高々と掲げるという「立派な仇討ち」がなされました。 その二年後、仇討ちの縁者を名乗る若侍が木挽町へ訪れ、事件を目撃した芝居小屋の関係者たちから、当時の話とその人生を聞き始めます。各章ごとに語り手が替わり、彼らの証言や語られなかった過去が少しずつ明らかになります。
物語の語り手は五人が中心です。例えば、木戸芸者・吉原生まれの一八、立師として武家を出奔した与三郎、女形かつ火葬場の番人出身のほたる、小道具職人の妻・お与根、そして旗本次男から戯作者へ転じた金治。 彼らがそれぞれ、自らの来し方と「目撃・関与」したあの夜の仇討ちを語ることで、ひとまず「見たまま」の事件像から、底に横たわる事情や人間模様が浮き上がってきます。
語り手を複数に分ける構成が特徴であり、読者は「一人の語り→次の語り」へと移るたびに、証言者の視点や価値観が変化し、事件そのものが揺らいで見えてくる仕掛けになっています。
本作の大きなテーマの一つに「身分・職業・性別を超えた生き場の模索」があります。芝居小屋という、武家・町人・下層とも交錯する場所を舞台に、語り手たちは「本来の身分」から逸脱、あるいは逸脱させられた者たちです。例えば与三郎は武家出身ながら立師に、ほたるは女形かつ火葬場育ちという境遇。 その中で起きた「仇討ち」は単なる復讐劇ではなく、彼ら自身の生の問いや、社会の歪みに対するささやかな抵抗とも重なります。
また、語りは軽妙さを備えつつ江戸の空気を伝える筆致で進行します。町人・芸者・武士といった異なる立場の語り口が混在することで、読者は江戸の舞台裏にいるような没入感を得られます。
最後に仇討ち事件そのものの「真相」が明らかになっていく構成です。誰が語っていたのか、何が語られていなかったのか、仇討ちという行為の意味が改めて問われます。多面的な証言から真実の輪郭が少しずつ姿を現すため、読み進めるほどに構図が変化していく点が興味深く感じられます。
永井氏は、江戸後期・文化・文政時代を回顧しながら、現代と通じる「窮屈な社会で不器用に生きる人々」の姿を描き出す意図を語っています。芝居小屋という「規範から外れがちな人々」が集う場を通じて、その時代の被差別・被抑圧的な構造にも光を当てています。
上記構成はミステリの趣も帯びており、仇討ちの「誰にとって正義か」という問いを読者の側にも突きつけます。実際に複数の読書レビューで「ミステリ要素」「謎解き感」が高く評価されています。
語り手が次々と変わるため、人物の来歴や語りの背景に注目すると物語の深みが増します。仇討ちという事件そのものより、語られ方そのものにこそ「事件の意味」が隠れている構造です。撮られざる視点=語られなかった事情を読み解く喜びがあります。
また、芝居小屋の稽古場、衣装部屋、長屋、枡席といった場面設定が各幕ごとに異なり、江戸の演劇文化に関心がある読者にはその裏側も魅力となります。舞台芸能という業界の構造、人間関係、偶然の巡りあわせが事件にどう絡んだかをあれこれ想像しながら読むと更に深まります。
この作品は「仇討ち」そのもの以上に、その背後にある人々の生き様を鮮明に照らし出す構造を持っています。読み終えた後、登場人物それぞれが抱えた背景や語り口が、事件を語る「証言」から「人生」へと変化していることに気づきます。仇討ちを成し遂げた若衆の姿を追うだけではなく、彼を取り巻く語り手たちの声に耳を澄ますことで、作品が立ち上がる立体的な世界が見えてくるはずです。
時代小説、歴史小説等の買取について
「どこに売ったってたいして変わらないだろう。」そう思っていませんか?規模が大きいほぼ確かにその傾向があります。規模が小さめのお店についてはどうでしょうか。実は確かなプロが在中する小規模なお店なら違いが如実です。適切なお店をまだあまりご存じないかもしれません。ポイントは小規模で専門家のいるお店を選択することです。